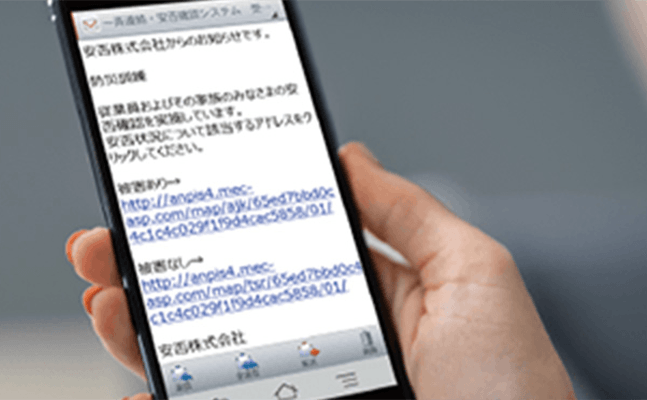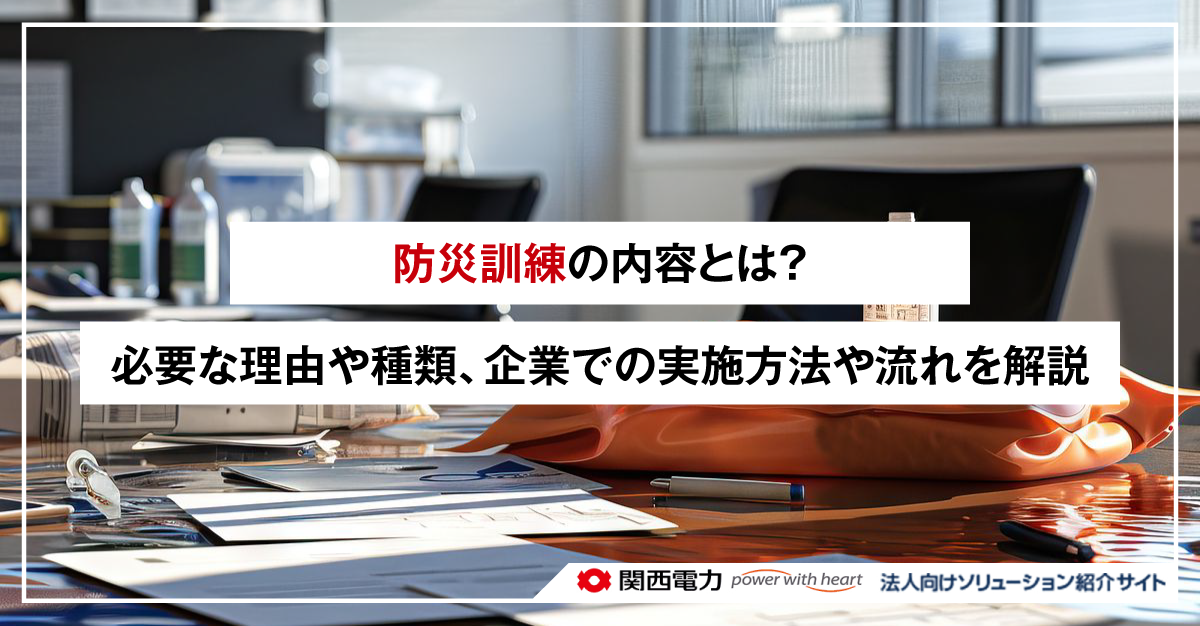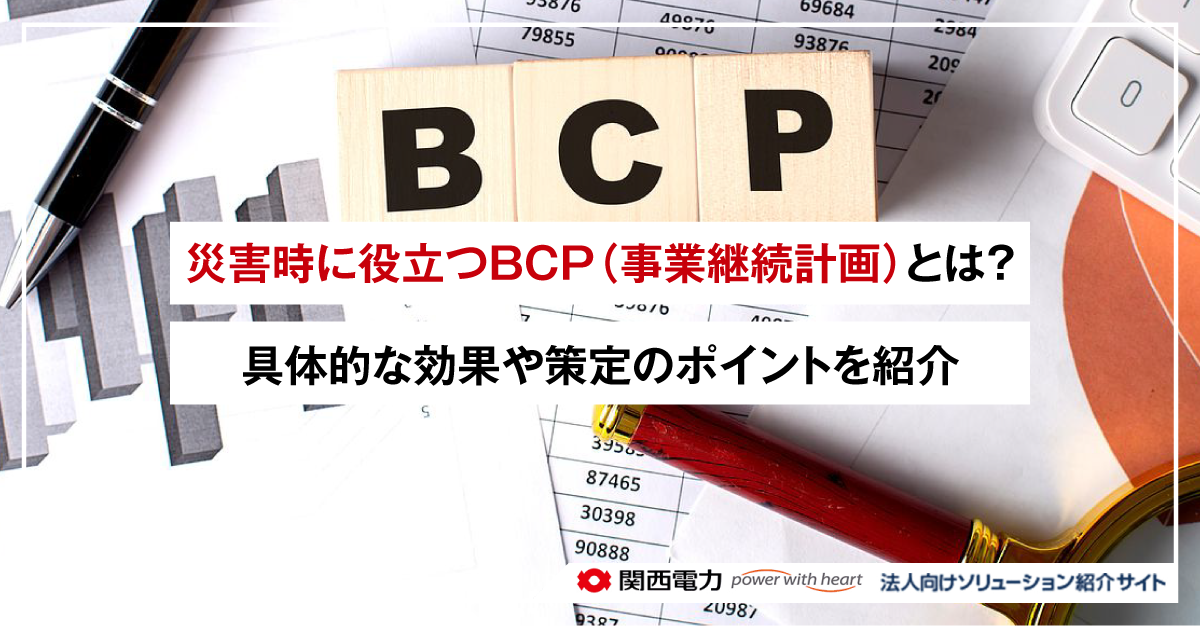消防設備点検費用の相場はいくら?建物別の費用体系や安く抑えるコツを紹介
2025.3.21
関連キーワード:
- 消防設備点検費用
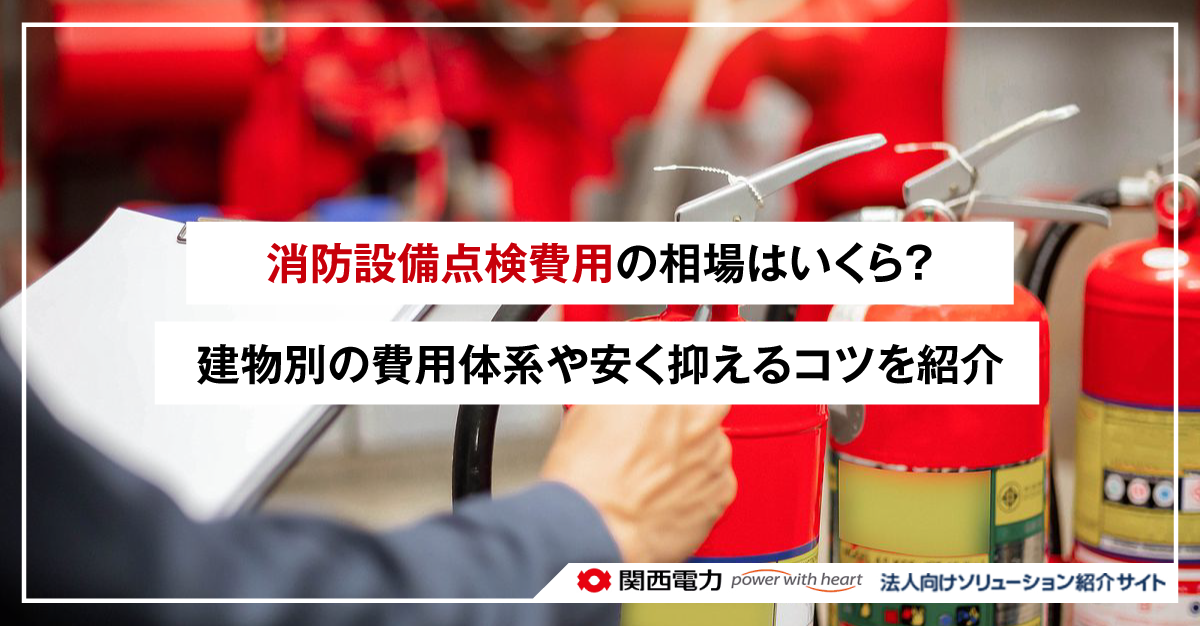
目次
消防設備点検の実施義務は法律に定められています。怠った場合の罰則も設けられているため、忘れずに実施することが大切です。
この記事では、消防設備点検費用の相場や点検の種類、点検項目を詳しく紹介します。業者の選び方や費用を抑えるコツも紹介するので、消防設備点検の実施を考えている方は参考にしてください。
従業員の安否確認から
集計までを自動化
災害時の迅速な初動対応が可能に
安否確認システム 「ANPiS」 は気象庁と連携し、 災害が発生するとメール等が自動で配信され、
従業員の安否や出社可否の確認結果を自動集計します。

- ※1 2019年8月(サービス開始)~2024年9月現在の実績です。受信側の要因を除きます。
- ※2 オプションでLINEの一斉配信も可能です。
消防設備点検費用の相場
消防設備点検費用は点検項目や建物の用途、規模によって異なる他、依頼する業者によっても費用体系が異なります。一般的な相場は以下のとおりです。
| 延べ面積 | 施設 | ||
|---|---|---|---|
| 商業施設 | 非商業施設 | マンション | |
| ~300m2 | 1〜3万円 | 1〜2万円 | 1〜2万円 |
| 300~1,000m2 | 2〜10万円 | 2〜6万円 | 2〜6万円 |
| 1,000~2,000m2 | 7〜15万円 | 3〜8万円 | 3〜8万円 |
| 2,000~3,000m2 | 10〜30万円 | 7〜10万円 | 5〜10万円 |
| 3,000~5,000m2 | 16〜40万円 | 10〜20万円 | 7〜20万円 |
| 5,000~10,000m2 | 25〜60万円 | 15〜30万円 | 10〜30万円 |
| 10,000~25,000m2 | 40〜100万円 | 30〜60万円 | 20〜60万円 |
| 25,000m2〜 | 55万円〜 | 40万円〜 | 30万円〜 |
消防設備点検は特定の商品の購入ではなく点検作業のため、内訳の大半が人件費や移動費等です。費用は各社が設定する料金に依存するため、複数の業者から見積もりを取り比較しましょう。
そもそも消防設備点検とは?
消防設備点検とは、建物内に設置されている消防設備が適切に機能しているかを定期的に確認する作業を指します。
消防設備は、火災が発生した際に被害を最小限に抑えるために欠かせない設備です。火災が発生した際に有効に機能するよう、防火対象物の管理者は消防設備を点検し、消防長または消防署長に報告しなければならないと消防法第十七条の三の三「消防用設備点検報告制度」に定められています※。
点検項目や点検頻度が詳しく定められているため、消防法に則って点検を行いましょう。詳しくは以降で紹介します。
- ※出典:e-Gov法令検索 「消防法」
消防設備点検の実施者と建物の分類
消防設備点検の実施者は建物の規模や分類によって異なります。例えば、以下に該当する建物では、消防設備士または消防設備点検資格者による点検が必要です※。
- ●延べ面積 1,000m2以上の特定防火対象物
- ●延べ面積 1,000m2以上の非特定防火対象物で消防長または消防署長が指定したもの
- ●特定一階段等防火対象物
- ●全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設置されている防火対象物
上記の条件に該当しない場合、法律上資格者以外でも点検できますが、安全性の面から資格者による点検が推奨されています。
なお、特定防火対象物と非特定防火対象物は以下の頻度で点検結果の報告が必要です。建物用途(規模にかかわらず)によって決められた期間ごとに所轄消防署に報告する義務があります。
| 区分 | 報告の頻度 | 用途例 |
|---|---|---|
| 特定防火対象物 | 1年に1回の報告 | 物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店等、不特定多数の人が出入りする建物 |
| 非特定防火対象物 | 3年に1回の報告 | 工場、事務所、共同住宅、学校、駐車場等 |
- ※出典:国土交通省 「法定点検等の実施」
なお、報告の頻度とは別に、点検の種類(機器点検もしくは総合点検)ごとの点検頻度も定められています。以降で詳しく紹介するので参考にしてください。
消防設備の定期点検(法定点検)義務

消防設備の点検頻度は以下のとおりです。
- ●機器点検は6ヶ月に1回
- ●総合点検は1年に1回
それぞれ詳しく紹介します。
機器点検は6ヶ月に1回
機器点検とは、設備の外観や簡易な機能確認を行い、不具合や異常がないかを確認する点検です。主に目視や作動操作と手動操作による判別によって、消防設備が適切な状態に保たれているか確認します。
具体的には、消防用設備等の非常電源や動力消防ポンプが正常に作動するか、配置は適切か、損傷等の有無はないか等、その他外観から判別できる事項をチェックします。設備ごとの細かい点検項目は総務省消防庁が提供している様式で確認可能です。
例えば、消火器具は以下を確認するように定められています。
| 点検項目 | 備考 |
|---|---|
| 設置状況 | 設置場所、設置間隔、適応性、耐震措置 |
| 表示・標識 | - |
| 消火器の外形 | 本体容器、安全栓の封、安全栓、使用済みの表示装置、押し金具・レバー等、キャップ、ホース 、ノズル・ホーン・ノズル栓、指示圧力計、圧力調整器 、安全弁、保持装置、車輪(車載式)ガス導入管(車載式) |
点検要領もダウンロード可能で、点検方法や点検結果の判定方法まで記載されています。
総合点検は1年に1回
総合点検とは、機器点検を含め、実際に設備のすべてもしくは一部を作動させ、機能を総合的に確認する点検です。総合点検は、消防法により1年に1回行うことが義務付けられています。
消火器具や火災報知器、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備等、機器点検でも確認する設備に加え、設備の配線を確認します。点検項目や点検要領は機器点検と同様に総務省消防庁のホームページで確認可能です。
なお、前述のとおり総合点検には機器点検も含まれているため、半年おきに機器点検と総合点検を交互に行えば、法定点検義務の回数(機器点検は年2回、総合点検は年1回)を遵守できます。
消防設備点検を怠った場合の罰則
消防法には点検に関する罰則も定められています。例えば、消防用設備等の点検報告に関して、虚偽の報告を行った者、または報告しなかった者は、30万円以下の罰金または拘留に処されます。
違反行為をした人だけではなく、当該違反者に対して監督責任を有する法人も30万円以下の罰金に処されるため注意しましょう。
消防設備点検項目の具体例
消防設備の点検項目は細かく分類すると全部で30種類以上あります。点検表のフォーマットは総務省消防庁のホームページからダウンロードでき、点検した結果を記入・添付して提出します。点検項目を大まかに分類すると以下のとおりです。
- ●消火設備
- ●警報設備
- ●避難器具
- ●消防用水
- ●消火活動上必要な設備
それぞれ簡潔に紹介します。
消火設備
消火設備とは、火災が発生した際に火を素早く消し止め、被害を最小限に抑えるために設置される設備を指します。消火設備の具体例は以下のとおりです。
- ●屋内消火栓設備
- ●屋外消火栓設備
- ●粉末消火設備
- ●スプリンクラー設備
- ●水噴霧消火設備
- ●不活性ガス消火設備
- ●泡消火設備
- ●消火器具・簡易消火用器具
- ●動力ポンプ消火設備
警報設備
警報設備とは、火災や災害等の異常を感知し、周囲に知らせるための設備を指します。具体例は以下のとおりです。
- ●自動火災報知設備
- ●ガス漏れ火災警報設備
- ●漏電火災警報器
- ●非常警報設備(非常ベル・放送設備)
- ●消防機関へ通報する火災報知設備
- ●非常警報器具(警鐘・携帯用拡声器等)
- ●住宅用火災警報器
避難器具
避難器具(避難設備)とは、火災や地震等の緊急時に建物から安全に脱出し、命を守るために使用される設備や道具を指します。具体例は以下のとおりです。
- ●避難はしご
- ●緩降機
- ●すべり台
- ●避難ロープ
- ●避難橋
- ●避難用タラップ
- ●救助袋
消防用水
消防用水とは、火災時に消火活動を行うために確保されている水を指します。消火栓や消防車、スプリンクラー設備等の消火装置で使用され、火災の被害を抑える重要な役割を果たす設備です。
火災発生時に消火活動が適切に行えるよう、消防用水の設置場所や構造は細かく規定されています。消防用水では、以下の内容を確認します。
- ●貯水槽
- ●水量
- ●水状
- ●給水装置
- ●周囲の状況
- ●吸管投入口
- ●採水口
- ●標識
消火活動上必要な設備
消火活動上必要な施設とは、火災やその他の災害時に、防火対象物の構造、形態等から消防活動が困難と予想されるもの(高層階・地下階・地下街等)に対して、消防隊が効果的に活動できるように設置が義務付けられている設備や施設を指します。
具体例は以下のとおりです。
- ●排煙設備
- ●連結散水設備
- ●連結送水管
- ●非常用コンセント設備
- ●無線通信補助設備
消防設備点検を依頼する業者選びのポイント
消防設備点検は項目が多く、有資格者が必要な場合もあるため、業者に依頼するケースも多いでしょう。消防設備点検を依頼できる業者は複数あるため、選ぶ際には以下の点に注目して選んでください。
- ●料金形態は明瞭か
- ●最新の消防法に沿った点検を行ってくれるか
- ●実績豊富かつ有資格者が在籍しているか
- ●柔軟な対応が可能か
- ●書類作成や設備の修理・交換にも対応しているか
点検にかかる費用や基本料金、追加料金等は業者によって異なります。想定しない金額の請求によるトラブルを避けるためには、事前に総額を教えてくれる業者や料金形態が明瞭な業者を選ぶことが大切です。
その他、サービスの丁寧さや対応の速さ、実績の豊富さもチェックしましょう。また、点検だけではなく、提出が必要な報告書の作成をしてくれる業者を選ぶと自社の業務負担を減らせます。点検時に不具合が確認された際、修理や交換に対応してくれる業者であればより安心です。
消防設備点検費用を抑えるコツ
消防設備点検費用を抑えるコツは以下のとおりです。
- ●見積もり料金や出張料金がかからない業者を選ぶ
- ●点検はできるだけまとめて行う
- ●複数の業者から見積もりをとってから選ぶ
以降で詳しく紹介します。
見積もり料金や出張料金がかからない業者を選ぶ
消防設備点検の費用を抑えるためには、見積もり料金や出張料金が無料の業者を選ぶことが大切です。一部の業者では見積もりや出張に別途料金が発生する場合がありますが、無料で対応してくれる業者も多くあります。
近隣の業者を選べば移動コストがかからず、トータルの費用を削減しやすくなるでしょう。作業にかかる費用とあわせて、追加で発生するおそれがある料金はよく確認しておくことが大切です。
点検はできるだけまとめて行う
消防設備点検費用の内訳の大半は人件費や移動費のため、設備ごとに分けて依頼するよりも、複数の設備を一度に点検してもらう方が費用を抑えられます。一括点検にすることで、業者側も作業時間や人件費を削減できるためです。
一括で点検を依頼すると、割引を適用してくれる可能性もあるため、一度問い合わせてみるとよいでしょう。
複数の業者に見積もりを取ってから選ぶ
複数の業者から見積もりを取ることも大切です。業者によって料金設定やサービス内容が異なるため、比較して選ぶとコストを抑えられるかもしれません。
ただし、費用の安さだけで選ぶと後悔するおそれもあるため注意が必要です。サービスの質やアフターサポートも確認し、総合的に判断してください。
消防設備の点検とあわせて準備しておきたい災害時の備え

災害に備えるうえで、消防設備の定期点検は欠かせません。
例えば、災害による停電対策として非常用発電機を保有している企業は、定期的に非常用発電機の負荷試験を実施していないと、いざ稼働させた際に動作不良や異常停止を起こすリスクがあります。
消防法では、1年に1回の総合点検時に、負荷試験等により非常用発電機の運転性能を確認することが義務化されています。さらに、連続運転性能や換気状況を確認するため、定格出力の30%以上の負荷を一定時間与える負荷試験の実施が推奨されています。
関西電力では、その条件を満たし、かつ停電作業が不要な「模擬負荷試験」のサービスを行っているため、ご検討されている方は一度問い合わせてみてはいかがでしょうか。
しかし、個人や企業がいざという時に命を守るためには、消防設備だけでは不十分です。
特に企業は自分の命だけではなく、従業員の安全や事業の継続性を守る使命もあります。そのため、以下の準備や計画も消防設備の点検と同様に重要です。
- ●防災用品・備蓄品の用意
- ●ハザードマップの確認
- ●BCPの策定
- ●安否確認システムの導入
火災は自然災害によっても起こるおそれがあります。日本は自然災害が多い国であり、近年では気候変動により台風や大雨の頻度が高まっている他、大地震のリスクの高まりも懸念されています。
そのため、火災に備え消防設備を点検するのに加え、自然災害に備えておくことも大切です。万が一の場合を想定して防災用品・備蓄品を用意し、危険なエリアや避難場所が確認できるハザードマップは全従業員に共有しておきましょう。
事業の継続性も確保するためにはBCPの策定も効果的です。BCP(Business Continuity Plan、事業継続計画)とは、自然災害やシステム障害、パンデミック等の緊急事態が発生した際に、事業の継続性を確保し、損害を最小限に抑えるための計画を指します。BCPは災害・緊急事態を包括的に考慮した行動計画のため、火災以外の災害にも応用可能です。
また、安否確認システムは火災をはじめとする災害に役立つツールです。安否確認システムは災害や緊急時に迅速に従業員の安全を把握できる他、安否確認にともなう業務負担を大幅に軽減できます。
消防設備の点検に加え、災害・緊急時に役立つ備えとして、防災用品・備蓄品の用意やBCPの策定、安否確認システムの導入も検討してみてください。
BCPについてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
関連記事:災害時に役立つBCP(事業継続計画)とは?具体的な効果や策定のポイントを紹介
災害時のスムーズな安否確認なら「ANPiS」がおすすめ
災害時への備えとして安否確認システムを導入するなら、「ANPiS(アンピス)」 を検討してはいかがでしょうか。ANPiSは関西電力が提供している安否確認システムです。災害・緊急時に必要な機能を備えながら、シンプルで使いやすい操作設計となっています。
比較的低コストで導入でき、従業員への安否確認メールの自動配信や、回答結果の自動集計が可能です。手動でメール配信することもでき、部署やグループに絞った連絡にも活用できます。災害・緊急時に従業員の安否確認を効率的に行えれば、その他の対応業務に人的リソースを集中できます。
火災だけではなく、地震、台風、豪雨、パンデミック等さまざまな災害・緊急事態に応用可能です。ANPiSでは以下の機能がご利用いただけます。
【利用できる機能】
- ●気象庁情報と自動連携(地震、特別警報等)
- ●従業員の回答結果の自動集計
- ●未回答者への自動再配信
- ●手動配信によるパンデミック対応
- ●アンケートや会議の出欠確認等平常業務への応用
- ●安否登録の際のID・パスワードスキップ
- ●部門横断グループ設定
- ●個人情報の秘匿性確保
- ●家族の安否登録機能
- ●LINE配信(有償オプション)
初期費用は無料、月額6,600円(税込)から利用可能で、企業の規模やニーズにあわせて2つのプランが用意されています。
| ご利用人数 | スタンダードプラン※1(税込) | ファミリープラン※2(税込) |
|---|---|---|
| ~50名 | 6,600円 | 6,985円 |
| ~100名 | 9,900円 | 10,670円 |
| ~150名 | 13,200円 | 14,355円 |
| ~200名 | 15,400円 | 16,940円 |
| ~300名 | 17,600円 | 19,910円 |
| ~400名 | 19,800円 | 22,880円 |
| ~500名 | 22,000円 | 25,850円 |
| 501名〜 | 100名ごとに+2,200円 | 100名ごとに+2,970円 |
ANPiSはWebからお申込み可能です。お申込みから利用開始までは最短1ヶ月と、スピーディーに導入できます。
また、事前に2週間の無料トライアルが利用でき、実際の使用感を試すこともできます。安否確認システムの導入を検討しているなら、関西電力に相談してみてはいかがでしょうか。
- スタンダードプランは、従業員とその家族へメール配信するプランです。
- ファミリープランは、スタンダードプランに加えて、家族の応答内容を家族内で共有することができます。
なお、家族への安否確認メールは管理者による手動配信となります。
消防設備点検費用は点検内容や建物の規模によって異なる
消防設備点検費用の相場は以下のとおりです。
| 延べ面積 | 施設 | ||
|---|---|---|---|
| 商業施設 | 非商業施設 | マンション | |
| ~300m2 | 1〜3万円 | 1〜2万円 | 1〜2万円 |
| 300~1,000m2 | 2〜10万円 | 2〜6万円 | 2〜6万円 |
| 1,000~2,000m2 | 7〜15万円 | 3〜8万円 | 3〜8万円 |
| 2,000~3,000m2 | 10〜30万円 | 7〜10万円 | 5〜10万円 |
| 3,000~5,000m2 | 16〜40万円 | 10〜20万円 | 7〜20万円 |
| 5,000~10,000m2 | 25〜60万円 | 15〜30万円 | 10〜30万円 |
| 10,000~25,000m2 | 40〜100万円 | 30〜60万円 | 20〜60万円 |
| 25,000m2〜 | 55万円〜 | 40万円〜 | 30万円〜 |
総合点検は年に1回、機器点検は半年に1回(年2回)行うことが法律によって義務付けられているため、法律に従って点検を実施しましょう。
消防設備点検は人命を守る重要な役割があり、火災や災害への基本的な備えになります。従業員の命や事業の継続性も重要となる企業では、あわせて安否確認システムの活用もおすすめです。
安否確認システムの導入なら 「ANPiS」 をご検討ください。「ANPiS」は初期費用無料、月額6,600円(税込)から利用可能です。2週間の無料トライアルも可能なので、災害に備えて安否確認システムの導入を検討している場合はご相談ください。
従業員の安否確認から
集計までを自動化
災害時の迅速な初動対応が可能に
安否確認システム 「ANPiS」 は気象庁と連携し、 災害が発生するとメール等が自動で配信され、
従業員の安否や出社可否の確認結果を自動集計します。

- ※1 2019年8月(サービス開始)~2024年9月現在の実績です。受信側の要因を除きます。
- ※2 オプションでLINEの一斉配信も可能です。

監修者 三沢 おりえ(みさわ おりえ)
総合危機管理アドバイザー
防犯・防災、護身術の講演会やセミナー、イベント、メディア対応等幅広く活動。日本一非常食を食べていると自負する非常食マイスターでもある。総合防犯設備士、危機管理士、防災士。
サービス概要資料
安否確認システム
「ANPiS」
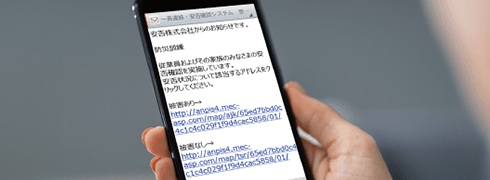
BCP策定の第一歩は、安否確認から!関西電力が提供する「安否確認システム(ANPiS)」のサービス概要をご紹介します。
資料の一部をご紹介
- 安否確認システム(ANPiS)とは
- 選ばれる理由
- サービスの特徴
- よくあるご質問
資料ダウンロードフォーム
■個人情報の取扱いについて
◇個人情報の利用目的
弊社では、「個人情報保護方針」内の「個人情報の利用目的」および「弊社が開催するセミナーの案内、弊社と提携する他社のセミナーの案内を行うために必要な範囲内で個人情報を利用いたします。
◇広告・宣伝メールの送信
弊社は、お申込フォームで入力いただいたメールアドレスあてに、広告・宣伝メール(「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」に定める「特定電子メール」を指します。)を送信することがあります。また、お客さまから申し出により、速やかに配信を停止します。