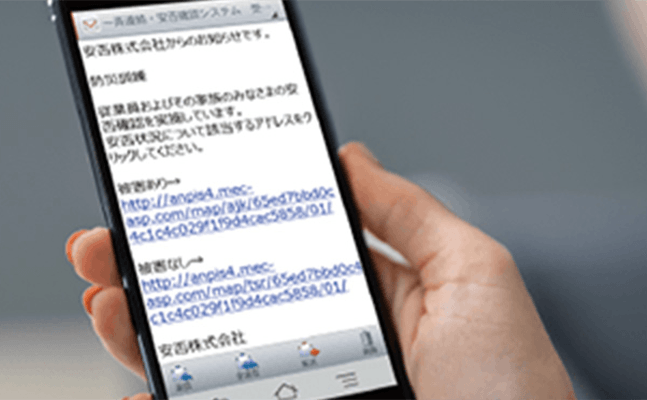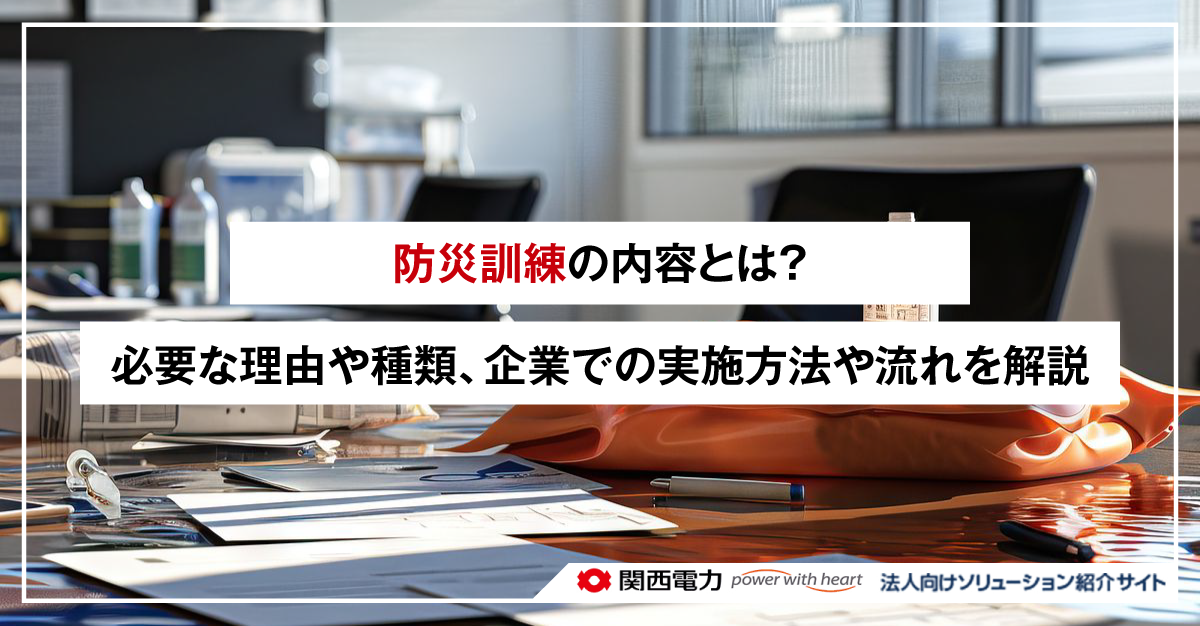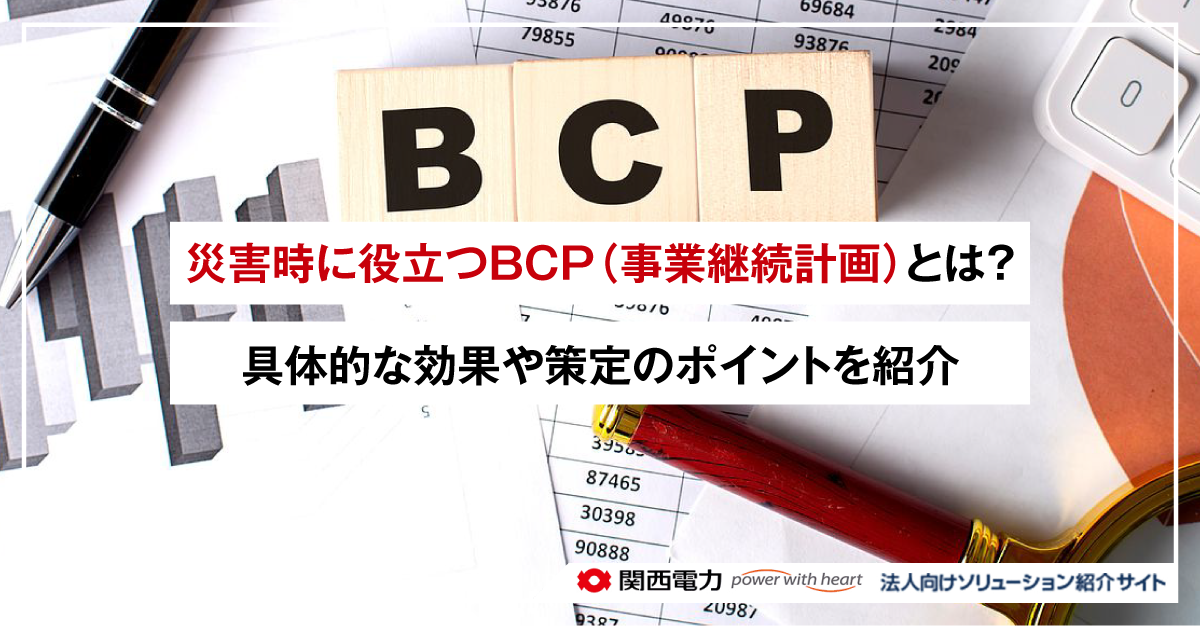従業員の健康管理は企業の義務?具体的な方法や国の支援制度を解説
2025.5.19
関連キーワード:
- 従業員健康管理

目次
従業員の健康管理が必要なことは理解しているものの、具体的に何から始めればよいかわからない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、従業員の健康管理が必要な理由、具体的な方法等について詳しく解説します。
従業員の健康管理に活用できる国の支援制度も紹介するため、ぜひ参考にしてください。
従業員の安否確認から
集計までを自動化
災害時の迅速な初動対応が可能に
安否確認システム 「ANPiS」 は気象庁と連携し、 災害が発生するとメール等が自動で配信され、
従業員の安否や出社可否の確認結果を自動集計します。

- ※1 2019年8月(サービス開始)~2024年9月現在の実績です。受信側の要因を除きます。
- ※2 オプションでLINEの一斉配信も可能です。
従業員の健康管理は企業の義務!
大前提として、企業には以下の2つの法律により従業員の健康や安全を守る義務があります。
- 1.労働契約法
- 2.労働安全衛生法
「労働契約法」 では、企業に対して「安全配慮義務」を求めることが明文化されていますが、企業が従業員への安全配慮義務を怠ったことによる罰則規定は設けられていません。しかし、過去の判例から企業に対して損害賠償の支払いを命じる判決が多数出ています。
一方、「労働安全衛生法」では、従業員の健康保持・促進のために行うべき措置として、安全管理者や衛生管理者、産業医等の選任、労働災害防止のための具体的措置等が規定されています。また、「安全衛生法」 には、安全配慮義務を怠った場合の罰則が定められているものがあります。
社員の健康管理を怠っている点が外部に漏れれば、企業イメージを損なうおそれがあるでしょう。従業員の労働生産性に直結する問題でもあるため、企業が積極的に従業員の健康管理を行うことが大切です。
「健康経営」 が企業にもたらすメリット
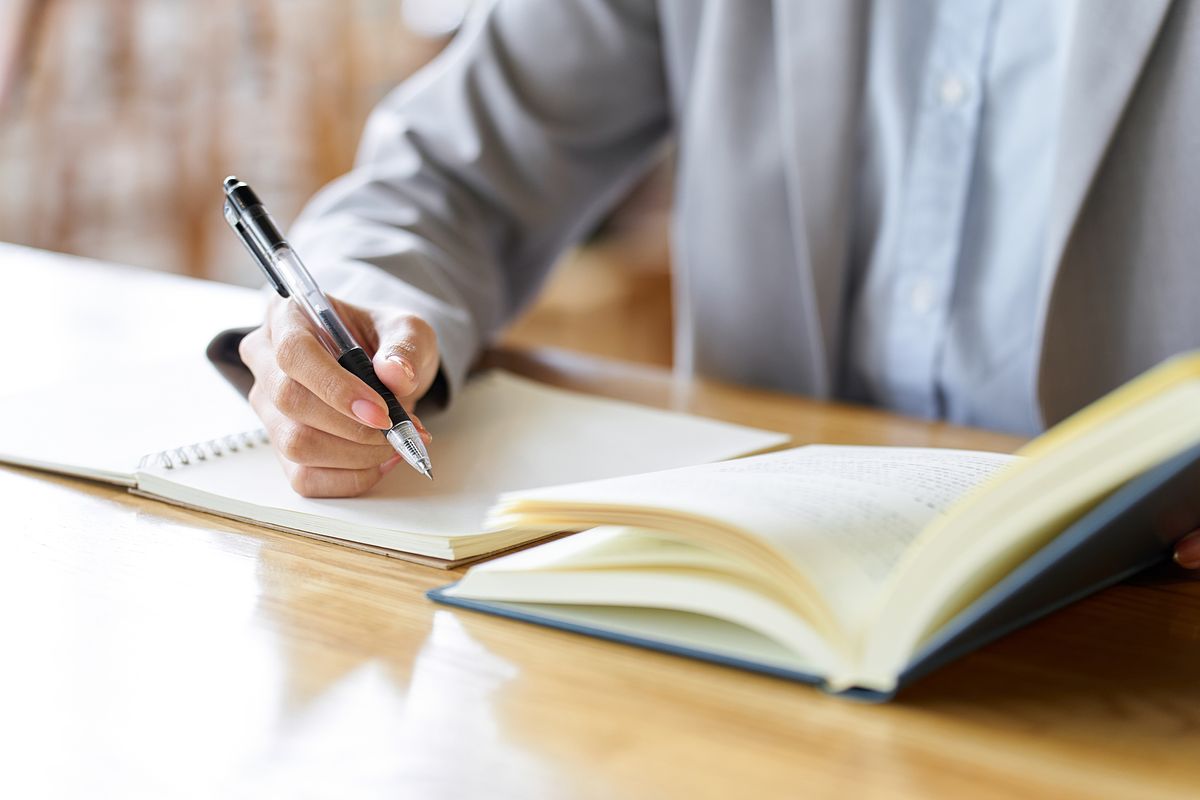
「健康経営」 とは、従業員の健康保持・促進の取り組みが、将来的に収益性等を高める投資であるという考えの下、経営的な視点から戦略的に従業員の健康管理に取り組むことを指します。
従業員の健康管理は企業の義務であり、以下のメリットもあるため、積極的に進めることが求められます。
生産性向上・将来的な収益性向上が期待できる
従業員の健康問題は、仕事のパフォーマンスに大きな影響を与えます。
そのため、企業が主体となり従業員の健康増進に取り組むことで、従業員や組織自体の活性化が期待でき、結果的に企業の業績向上や株価上昇にもつながる可能性があります。
企業価値の向上・ブランドイメージ強化につながる
経済産業省は、2014年から 「健康経営」 に力を入れている企業を選定する 「健康経営優良法人認定制度」 を採用しており、特に優良な企業を 「ホワイト500」 と認定しています。
認定法人は、健康経営優良法人の特別なロゴマークが使用可能となる他、自治体や金融機関でさまざまなインセンティブを受けることが可能です。例えば、補助金申請時に加点の優遇措置を受けられたり、融資において優遇利率が適用されたりする仕組みが設けられています。
近年の求職者は、給与面以外に労働条件や職場環境にも重きを置く傾向があり、上記のような認定を受けることで、企業のブランドイメージ強化にもつながります。
企業が従業員の健康管理を行う方法・ポイント
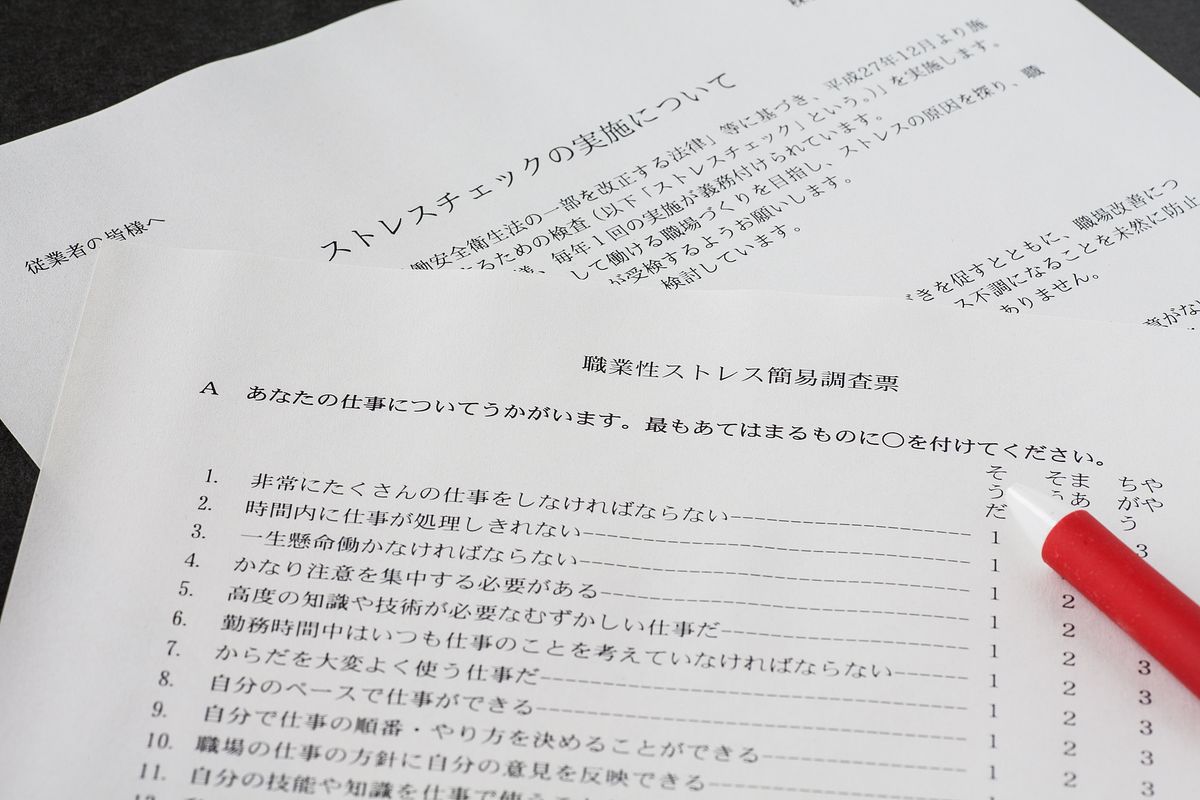
企業が従業員の健康管理を行う方法として、以下が挙げられます。
- ●労働時間の把握・長時間労働の是正
- ●健康診断の実施
- ●ストレスチェック制度の導入
- ●職場環境の整備(衛生推進者・衛生管理者の選任、衛生委員会の設置、産業医の選任)
- ●従業員用相談窓口の設置
- ●健康意識向上を目指す研修やセミナーの実施
- ●福利厚生の拡充
- ●安否確認システムの導入
それぞれの取り組みで重視すべきポイントや具体例を解説します。
労働時間の把握・長時間労働の是正
労働基準法には従業員の労働時間の上限が定められており、詳細は以下のとおりです。
- ●時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
- ●時間外労働と休日労働の合計が2〜6ヶ月平均で月80時間以内
- ●違反した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
長時間労働は肉体的にも精神的にも負担がかかり、さまざまな健康問題を引き起こす原因となるため、労働災害につながるおそれがあります。企業は従業員の長時間労働が常態化していないか把握するとともに、長時間労働を是正することが必要です。
従業員の労働時間を把握する主な方法としては、タイムカードによる記録やパソコン等のログイン・ログアウト時間を基にする方法が挙げられます。
また、上記の方法による労働時間の把握が難しく、従業員に自己申告をしてもらう場合、事業者は従業員に対して適正に労働時間の自己申告を行うことの十分な説明が必要です。自己申告内容と実際の労働時間が合致するよう、必要に応じて実態調査を実施することもあります。
長時間労働者については、健康状況を把握したうえで医師による面接指導が必要です。業務内容を見直して作業の効率化や労働環境の改善に取り組み、必要に応じて人員の増員等の対策を行いましょう。
健康診断の実施
労働安全衛生法では、健康診断の実施(一般定期健康診断)を毎年1回義務付けています。
従業員が一人でもいる場合は健康診断を実施する義務が生じ、実施しない経営者は処罰を受ける場合があります。
健康診断は、病気の早期発見や早期治療につながるため、従業員の健康状態を把握するうえで大切です。
ストレスチェック制度の導入
ストレスチェックとは、従業員がストレスに関する質問票を記入し、自身のストレスがどのような状態にあるのかを調べる検査のことです。
ストレスチェックを実施することで、従業員のメンタルヘルス不調を未然に防止できたり、職場環境の改善につなげられたり等、さまざまなメリットがあります。
労働安全衛生法では、常時使用する労働者が50人以上の事業場において、毎年1回すべての労働者に対してストレスチェックを行うことを義務付けています。
ストレス感度が高い従業員がいる場合は、適宜カウンセリングの実施も必要です。
職場環境の整備
従業員の健康管理を行うには、社員が毎日過ごす職場環境の整備が重要です。
事務所内の温度や湿度が適正か、日当たりや風通しは悪くないか、十分な作業スペースや休憩スペースを確保できているか等、職場環境を整備する施策は数多く挙げられます。
また、職場環境を整備するためのひとつの基準として、次のような専門家や機関の設定等も必要です。
衛生推進者・衛生管理者の選任
職場環境を整備して従業員の健康を守るうえで、専門家による確認も必要不可欠です。
労働安全衛生法では、常時雇用する従業員が10人以上いる会社の経営者に対しては 「衛生推進者」、従業員が50人以上いる経営者に対しては 「衛生管理者」 の選任が義務付けられています。
衛生推進者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任する必要があり、事業場に専属の者を選任することが求められます。
ただし、労働安全コンサルタントや労働衛生コンサルタント、その他厚生労働大臣が定める者のうちから専任する場合は、この限りではありません。
一方、衛生管理者は、従業員の安全や健康を保持・推進するための業務を行うため、選任されるためには業種に応じた資格が必要です。
| 業種 | 資格 |
|---|---|
| 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業および清掃業 | 第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許または医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント、厚生労働大臣の定める者 |
| その他の業種 | 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント、その他厚生労働大臣が定める者 |
産業医の選任
産業医は、健康診断や面接指導等での健康管理、衛生教育等を行うとともに職場巡回を行い、必要に応じて経営者に対して勧告や助言・指導を行える医師のことです。
労働安全衛生法では、常時使用する従業員数が50人以上の事業場に対して、産業医を選任して職場巡視等の業務を実施するための権限を与えることを義務付けています。
産業医を選任することで従業員の健康管理を行いやすくなり、職場の健康意識の向上にもつながります。
選任できない場合は、最寄りの地域センターで登録産業医から産業保健サービスを受けることが可能です。
衛生委員会の設置
衛生委員会は、会社の役員クラスの役職員、衛生推進者、産業医、労働衛生に関して経験のある従業員の各委員で構成され、従業員の健康維持や安全を守るため労使一体となって行います。
労働安全衛生法では、従業員数50人以上の会社の経営者に対して、労使と産業医が参加する衛生委員会の設置が義務付けられています。
経営者が従業員の委員を指名する場合は、労働組合または従業員の過半数を代表する者の推薦に基づいて指名しなければなりません。
福利厚生の拡充
従業員のワークライフバランスを保つためにも、福利厚生の拡充は非常に有効です。
これまでの福利厚生制度は慶弔給付等が主でしたが、近年ではカフェテリアプラン(福利厚生予算を従業員にポイントで付与し、ポイントを消費して福利厚生を利用できるもの)を採用し、従業員が好みに応じたサービスを自由に選べる制度も増えています。
例えば、日本年金機構では、職員一人ひとりが自分らしい生活を送りながら働き続けられるように下記の福利厚生制度を整備しています。
- ●休日・休暇制度
- ●家賃補助
- ●育児サポート
- ●日本年金機構共済会 等
しかし、中小企業では福利厚生の拡充が困難な場合があるでしょう。その場合、市区町村単位で設立された 「中小企業勤労者福祉サービスセンター」 を活用する方法があります。
中小企業勤労者福祉サービスセンターに入会すると、企業は自社単体よりも安い経費負担で福利厚生の拡充を図ることが可能です。
従業員用相談窓口の設置
心や体の健康に不安がある場合、社内に相談できる窓口を用意することも重要です。
心身に関わる相談事は他人に知られたくないと考える方も多いため、プライバシーを尊重しつつメールや電話、SNS等、さまざまな方法で相談できる環境を整えましょう。
厚生労働省が公開する働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト 「こころの耳」 では、社内相談窓口設置までの流れを公開しているので、参考にしてください。
- 1.衛生委員会等にて検討、方針決定
- 2.必要に応じて、相談対応者への研修の実施
- 3.相談窓口の開設
- 4.従業員・家族への周知
- 5.相談対応
一方で、社内の相談窓口を利用することに抵抗を感じる従業員がいる可能性もあるため、社外相談窓口の設置をあわせて検討するのがおすすめです。
社外相談窓口を設置する方法として、従業員支援プログラム 「EAP(Employee Assistance Program)」の相談窓口サービスを提供する企業との契約や、厚生労働省の 「こころの耳相談窓口」の案内等が挙げられます。
社外窓口を利用する場合は、従業員の個人情報の取り扱いに関する事前確認を徹底しましょう。
健康意識向上を目指す研修やセミナーの実施
研修やセミナーを実施して、従業員自身の健康意識を高めることも大切です。
労働安全衛生法は、経営者に対し、従業員の健康の保持増進のために健康教育や健康相談等を含む措置を継続的・計画的に実施することを義務付けています。
また、従業員側もこれらの措置を利用して、健康の保持増進に努めなければならないとされています。
具体的には、産業医や保健師といった専門の講師を招いて研修やセミナーを開催し、日常生活の改善やメンタルヘルスのセルフケア方法を学ぶこと等が挙げられます。
近年では、従業員の健康意識向上を目的としたオンラインセミナーも開催されているため、積極的に取り入れることがおすすめです。
安否確認システムの導入
従業員の健康管理を行うには多大な時間と労力がかかります。そこで、従業員の健康状態をより効率的に把握する方法のひとつとして、安否確認システムの導入が挙げられます。
安否確認システムは、主に災害時に従業員の安否状況を確認するために使用されるツールですが、質問項目や配信タイミングを自由に変更できる安否確認システムであれば、従業員の健康状態の把握にも活用できます。回答結果を自動で集計できる安否確認システムもあり、導入すれば時間と労力の削減につながるでしょう。
従業員の健康管理に活用できる国の支援制度
従業員の健康管理を行う際は、国の支援制度を積極的に取り入れることも大切です。
以下の支援制度の特徴を解説します。
- ●中小規模事業場安全衛生サポート事業
- ●中小規模事業場安全衛生相談窓口
- ●各種補助金制度
中小規模事業場安全衛生サポート事業
中小規模事業場安全衛生サポート事業は、無料で安全衛生の専門家からアドバイスを受けられるサービスです。
メリットとして、職場環境の改善点を知ることができる点や、安全衛生水準を把握することで安全衛生水準が向上し生産性向上につながる点が挙げられます。
支援方法は 「個別支援」 と 「集団支援」 の2種類があり、両者を組み合わせて実施することも可能です。
申込みや問い合わせは、中央労働災害防止協会技術支援部業務調整課、または最寄りの地区安全衛生サービスセンターで受け付けています。
なお、中小規模事業場安全衛生サポート事業が受けられる対象は、労災保険加入の製造業や鉱業等に限られているため事前に確認しておきましょう。
中小規模事業場安全衛生相談窓口
中小規模事業場安全衛生相談窓口は、中小規模事業場が抱える課題や問題、悩み等の解決を手助けしてくれるサービスです。
相談窓口は全国各地に設けられており、専門的知見やノウハウを持った安全衛生の専門家がアドバイスを無料で行ってくれます。
営業時間は平日9 : 00〜17 : 00(12 : 00〜13 : 00を除く)で、祝日や年末年始を除きます。
| 窓口 | 住所 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 中小規模事業場安全衛生相談窓口(本部) | 東京都港区芝5-35-2 安全衛生総合会館9階 |
03-3452-6296 jisha-soudan@jisha.or.jp |
| 北海道安全衛生サービスセンター | 札幌市中央区南19条西9丁目2-25 | 011-512-2031 |
| 東北安全衛生サービスセンター | 仙台市青葉区上杉1-3-34 | 022-261-2821 |
| 関東安全衛生サービスセンター | 東京都港区芝浦3-7-12シグマビル1階 | 03-5484-6701 |
| 中部安全衛生サービスセンター | 名古屋市熱田区白鳥1-4-19 | 052-682-1731 |
| 中部安全衛生サービスセンター 北陸支所 | 富山市奥田新町8-1ボルファートとやま9階 | 076-441-6420 |
| 近畿安全衛生サービスセンター | 大阪市西区土佐堀2-3-8 | 06-6448-3450 |
| 大阪労働衛生総合センター | 同上 | 06-6448-3464 |
| 中国四国安全衛生サービスセンター | 広島市西区三篠町3-25-30 | 082-238-4707 |
| 中国四国安全衛生サービスセンター 四国支所 | 高松市番町3-3-17第1讃機ビル2階北側 | 087-861-8999 |
| 九州安全衛生サービスセンター | 福岡市博多区東光2-16-14 | 092-437-1664 |
各種補助金制度
従業員の安全を守るためにかかる費用の一部を助成する補助金制度があります。
以下で厚生労働省が公開する助成制度の一例を紹介します。
| 名称 | 内容 | 金額 | 補助事業者 |
|---|---|---|---|
| 高度安全機械等導入支援補助金 | 安全機能を有する移動式クレーン・ドラグショベル・ショベルローダーを導入する中小企業に対して安全装置の費用の一部を補助 | 対象経費の1/2(上限200万円) | 建設業労働災害防止協会 |
| エイジフレンドリー補助金 | 60歳以上の高齢者を雇用する中小企業事業者を対象に、安全衛生確保に係る取り組みについて費用の一部を助成 | 対象コースによって変動
|
一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会 |
| 受動喫煙防止対策助成金 | 労働者の健康を保護する観点から、事業場における受動喫煙防止のための効果的な措置を講じた事業主に対して助成 | 対象経費の2/3(上限100万円) | 都道府県労働局労働基準部(健康課または健康安全課) |
また、各都道府県や市区町村で独自の補助金や助成制度を行っている場合があります。詳細は、市区町村公式ホームページや役所の相談窓口までお問い合わせください。
効率的に従業員の健康管理を行うなら関西電力の「ANPiS(アンピス)」がおすすめ
従業員の健康管理を手作業で行うには多大な時間と労力がかかるため、作業を効率化するためにツールの導入が選択肢として挙げられます。
例えば、関西電力の安否確認システム 「ANPiS(アンピス)」 には、アンケート機能が備わっており、従業員に毎日体調を回答してもらうよう設定すれば、健康状態の把握・管理に役立てられます。比較的低コストで導入でき、部署やグループを絞った連絡にも活用可能です。
なお、災害時の従業員の安否確認ツールとしても使用でき、気象庁情報と連携して自動で安否確認メールを配信し、回答結果を自動で集計する等、災害時の初動対応を効率化します。その他、ANPiSでは以下の機能が利用できます。
【利用できる機能】
- ●気象庁の情報と自動で連携
- ●地域、震度、警報・注意報等種類に応じた配信設定
- ●従業員の回答結果を自動で集計
- ●未回答の従業員に対する自動再配信
- ●手動配信による柔軟な対応
- ●アンケートや会議の出欠確認等平常業務への応用
- ●安否登録の際のID・パスワードスキップ
- ●部門横断のグループ設定
- ●従業員家族の安否登録(最大4名まで)
- ●個人情報の秘匿性
- ●LINE配信 (有償オプション)
初期費用は無料、月額6,600円(税込)から利用可能で、企業の規模やニーズにあわせて2つのプランが用意されており、全国で利用可能です。
| ご利用人数 | スタンダードプラン※1(税込) | ファミリープラン※2(税込) |
|---|---|---|
| ~50名 | 6,600円 | 6,985円 |
| ~100名 | 9,900円 | 10,670円 |
| ~150名 | 13,200円 | 14,355円 |
| ~200名 | 15,400円 | 16,940円 |
| ~300名 | 17,600円 | 19,910円 |
| ~400名 | 19,800円 | 22,880円 |
| ~500名 | 22,000円 | 25,850円 |
| 501名〜 | 100名ごとに+2,200円 | 100名ごとに+2,970円 |
Webからお申込みができ、2週間の無料トライアルも可能なので、安否確認システムの導入を検討する場合は、相談してみてはいかがでしょうか。
- スタンダードプランは、従業員とその家族へメール配信するプランです。
- ファミリープランは、スタンダードプランに加えて、家族の応答内容を家族内で共有することができます。
なお、家族への安否確認メールは管理者による手動配信となります。
従業員の健康管理を徹底してより快適な職場環境に
大前提として、企業には労働契約法や労働安全衛生法の規定に則って従業員の健康や安全を守る義務があります。従業員の健康保持・促進の取り組みは、将来的な生産性向上や収益性向上にもつながる可能性があるため、積極的に取り組みましょう。
従業員の健康管理を効率的に行うために、関西電力の安否管理システム「ANPiS」を活用するのもおすすめです。
自社に適した方法で健康管理を徹底し、企業全体でより快適な職場環境づくりに努めましょう。
従業員の安否確認から
集計までを自動化
災害時の迅速な初動対応が可能に
安否確認システム 「ANPiS」 は気象庁と連携し、 災害が発生するとメール等が自動で配信され、
従業員の安否や出社可否の確認結果を自動集計します。

- ※1 2019年8月(サービス開始)~2024年9月現在の実績です。受信側の要因を除きます。
- ※2 オプションでLINEの一斉配信も可能です。

監修者 三沢 おりえ(みさわ おりえ)
総合危機管理アドバイザー
防犯・防災、護身術の講演会やセミナー、イベント、メディア対応等幅広く活動。日本一非常食を食べていると自負する非常食マイスターでもある。総合防犯設備士、危機管理士、防災士。
サービス概要資料
安否確認システム
「ANPiS」
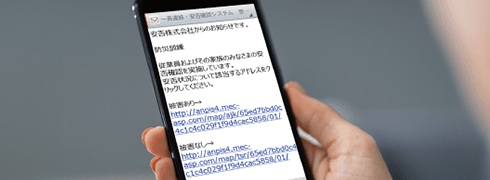
BCP策定の第一歩は、安否確認から!関西電力が提供する「安否確認システム(ANPiS)」のサービス概要をご紹介します。
資料の一部をご紹介
- 安否確認システム(ANPiS)とは
- 選ばれる理由
- サービスの特徴
- よくあるご質問
資料ダウンロードフォーム
■個人情報の取扱いについて
◇個人情報の利用目的
弊社では、「個人情報保護方針」内の「個人情報の利用目的」および「弊社が開催するセミナーの案内、弊社と提携する他社のセミナーの案内を行うために必要な範囲内で個人情報を利用いたします。
◇広告・宣伝メールの送信
弊社は、お申込フォームで入力いただいたメールアドレスあてに、広告・宣伝メール(「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」に定める「特定電子メール」を指します。)を送信することがあります。また、お客さまから申し出により、速やかに配信を停止します。