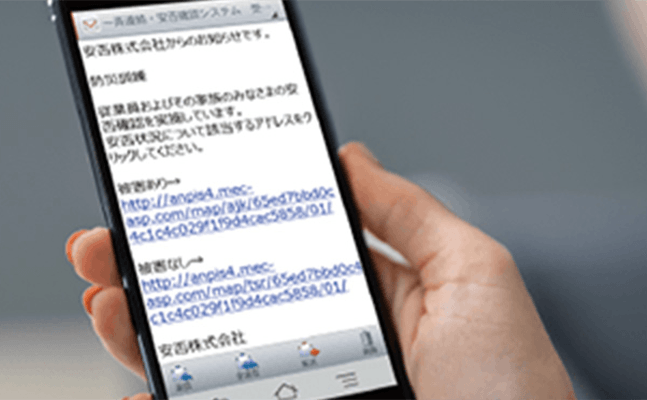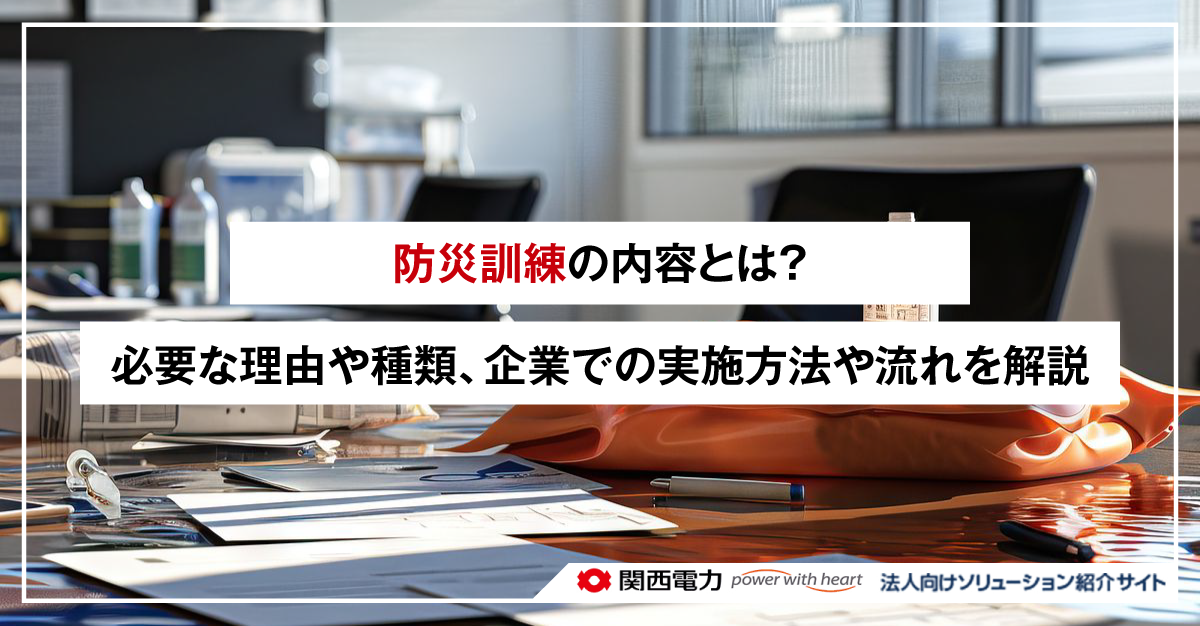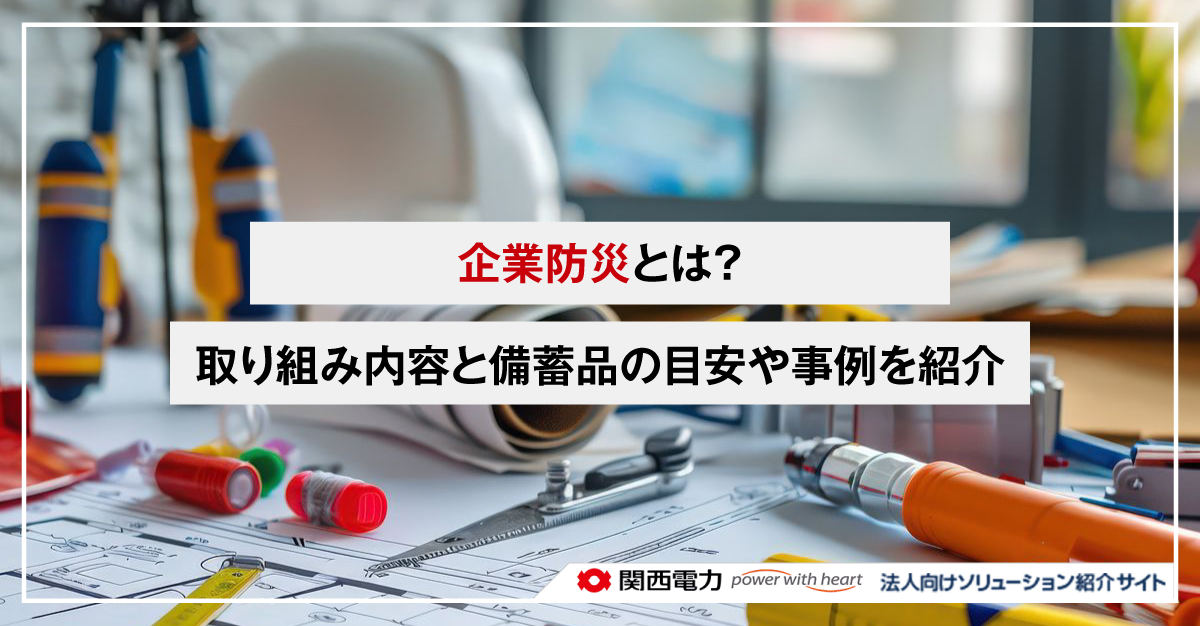災害時のBCP(事業継続計画)とは?対策の効果や策定のポイントを紹介
2025.9.16
関連キーワード:
- BCP
- 災害
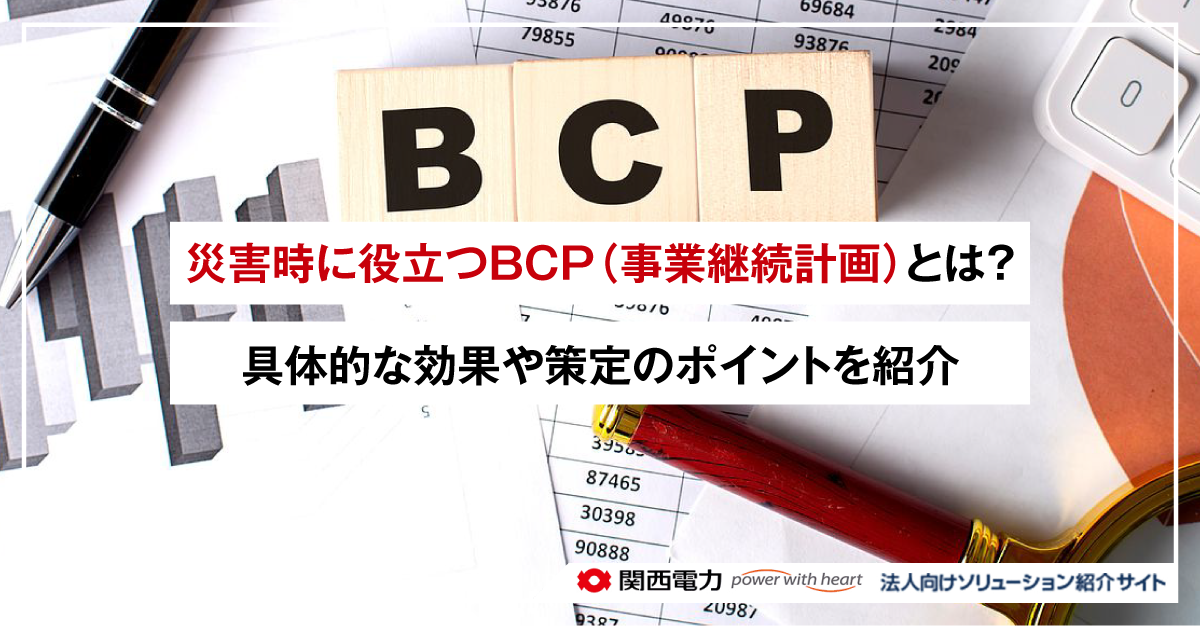
目次
BCP(事業継続計画)は、自然災害や感染症の流行等の予期せぬ事態から企業を守るための備えであり、事業への影響を最小限に抑え、迅速な復旧を果たすために重要な要素です。
近年の予期せぬ感染症の流行や大規模地震の発生リスクへの不安の高まりにより、BCPの策定がより重要視されています。
この記事では、BCPの具体的な効果や策定手順、策定時に押さえておくべきポイントを詳しく解説します。災害リスクへの対策は取引先に対してのアピールにもなり、企業価値を高めることにもつながるため、BCPの策定を考えている企業はぜひ参考にしてください。
従業員の安否確認から
集計までを自動化
災害時の迅速な初動対応が可能に
安否確認システム 「ANPiS」 は気象庁と連携し、 災害が発生するとメール等が自動で配信され、
従業員の安否や出社可否の確認結果を自動集計します。

- ※1 2019年8月(サービス開始)~2024年9月現在の実績です。受信側の要因を除きます。
- ※2 オプションでLINEの一斉配信も可能です。
災害時のBCPとは事業継続計画のこと
BCPとは 「Business Continuity Plan」 の略称で、事業継続計画のことです。
中小企業庁では、「企業が自然災害、大火災、テロ攻撃等の緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき行動や緊急時における事業継続のための方法、手段等を取り決めておく計画のこと」 と説明されています※。
企業は災害時・緊急時に事業の縮小や中断、倒産を避けるため、平常時からBCPを策定しておくことが大切です。また、大地震や感染症の発生等、災害や緊急事態が発生した際には、BCPに基づいて行動することで事業の早期復旧が図れます。
BCPとBCMの違い
BCP(事業継続計画)とBCM(事業継続マネジメント)は、どちらも緊急時に事業を継続させるために策定しておくものです。BCPは緊急時の損害を最小限に抑えつつ、事業の継続や復旧ができるような方法・手段を取り決めておく計画を指します。一方で、BCMはBCPを継続的に運用していく活動や管理の仕組みを指します。
つまり、BCPは計画自体を指すのに対し、BCMはBCPをいかに戦略的に運用していくかを意味する用語です。
BCPは 「Business Continuity Plan」、BCMは 「Business Continuity Management」 の頭文字を表しています。Bは事業(Business)、Cは継続(Continuity)で両方同じです。
BCPのPは計画(Plan)、BCMのMは経営や管理を意味するマネジメント(Management)で異なるので、PとMの違いを覚えておくと良いでしょう。
BCPとBCMの違いについてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
関連記事:BCPとBCMの違いとは?重要性や策定手順と運用時の注意点を解説
災害時のBCPと防災計画(災害対策マニュアル)の違い
防災計画を作成する主な目的は、「身体・生命の安全確保」 と 「物的被害の軽減」 です。本来継続すべき重要業務を、災害後も継続または早期復旧することを目指しているBCPは、防災計画がなされていることが大前提となります。
BCPは事業継続に焦点を当てている一方、防災計画は従業員の安全確保等に焦点を当てている点が大きな違いです。
防災計画には消防計画や避難確保計画、非常災害対策計画等が含まれます。防災計画はBCPの一部であり、内閣府の資料では、BCPでは防災計画に加えて以下の3点を策定する必要があると示しています※。
- ●優先業務の特定
- ●優先業務の復旧時間の設定
- ●代替手段の業務継続方法(業務の文書化)
災害対策にBCPの策定が求められる背景
日本は世界的にみても自然災害が多い国であり、近年では大規模地震のリスクへの不安も高まっています。BCPは、災害への備えとして策定が推進されている対策のひとつで、米国では一般的だった事業継続の考え方は、近年自然災害が多発している日本でも急速に普及しつつあります。
農林水産関係の過去10年の被害額は年々増加しており、自然災害による被害が継続して発生していることが分かります※1。災害は大規模地震だけではありません。1時間あたり降水量80mmを超える豪雨の発生回数も、全国的に増加しています※2。1976〜1985年の平均14回に対し、2015〜2024年は平均24回で約1.7倍の増加です。
地震をはじめとする自然災害や予期せぬ緊急事態の発生時に、事業復旧をスムーズに行うためにも、事前にBCPを策定しておくことが求められます。
BCP策定のガイドラインは、各業種に向けて関係する公的機関や団体から提供されているので、自社にとって参考となるガイドラインを確認しながら策定を進めると良いでしょう。
BCPの現状と課題
安全対策の重要性は高まっているものの、実際にBCPを策定できている企業は多くありません。日本商工会議所の2024年2月の資料を参考にすると、BCPの策定状況は以下のとおりです。
| BCPの策定状況 | 2024年2月 | 2022年9月 |
|---|---|---|
| 策定済み | 21.3% | 18.0% |
| 策定中 | 14.5% | 15.4% |
| 必要と思うが策定していない | 54.6% | 59.3% |
| そもそも必要ない | 9.6% | 7.3% |
2022年9月と2024年2月の調査を比べてみても、「策定済み」 と 「策定中」 の合計は33.4%から35.8%とわずかな増加にとどまっています。BCPを策定していない主な理由(複数回答可)は以下のとおりです。
- ●必要なノウハウ・スキルがないため(約47%)
- ●人的余裕がないため(約44%)
- ●家族経営等で企業規模が小さく、柔軟に対応できるため(約30%)
上記のデータからは、リスクに備ることの重要性を認識している企業が多い一方、安否確認システムの導入やBCPの策定に踏み切れない企業が一定数いることが伺えます。
BCPを策定している企業は、未策定企業に比べ、早期に事業復旧に至るとの調査結果も出ています。調査結果によると、被災後、BCPを策定している企業のうち、約1週間以内に事業復旧に至る割合は約9割であるのに対し、未策定企業においては約6割にとどまりました※。
また、事業復旧まで約2週間〜数ヶ月と、長期の時間を要した企業の割合も、未策定企業のほうが高い結果が出ています。
この調査結果からも、BCPの策定は、被災後の早期復旧に有効であることが分かります。以上をふまえると、BCP策定の必要性や効果を企業側が理解し、積極的に推進していくことが今後の課題に挙げられます。
BCPの策定が義務化されている事業者の例
一部の事業者には、BCPの策定が義務付けられています。
- ●災害拠点病院(2017年より義務化)
- ●介護サービス事業者(2024年4月より完全義務化)
- ●保育所等の児童福祉施設
以降で詳しく紹介します。
災害拠点病院(2017年より義務化)
災害拠点病院はBCPの策定や定期的な訓練が義務付けられています※。
災害拠点病院の要件を満たす場合、「被災後、早期に診療機能を回復できるよう、業務継続計画の整備を行っていること」「整備された業務継続計画に基づき、被災した状況を想定した研修及び訓練を実施すること」 等、定められた運営体制を構築する必要があります。
介護サービス事業者(2024年4月より完全義務化)
介護サービス事業者は、2021年4月の介護報酬改定によりBCPの策定が義務化され、2024年4月以降はすべての事業所で策定が求められています※。
BCPを策定する際のサポートとして、厚生労働省からはガイドラインが提供されています。
介護施設・事業所におけるBCPについてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
関連記事:介護施設・事業所におけるBCPとは?具体的なガイドラインと策定方法等を解説
保育所等の児童福祉施設(努力義務)
保育所等の児童福祉施設に対しては、新型コロナウイルスを契機に、感染症流行時等の業務継続についての見直しが行われました。
2023年4月以降、BCPの策定や訓練が努力義務として定められています※。児童福祉施設の設備運営基準等の一部を改正する省令では、BCPの策定・訓練実施とともに 「感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための研修・訓練を実施すること」 が記載されています。
BCPが災害対策に重要な理由や導入効果・メリット
BCPの導入によって得られる具体的な効果やメリットは以下のとおりです。
- ●災害・緊急事態が発生しても迅速に対応できる
- ●従業員の雇用や顧客への供給を守れる
- ●企業価値や信頼が向上する
- ●企業の社会的責任を果たしていると評価される
- ●税制優遇等の公的支援を受けられる可能性が高まる
それぞれ詳しく紹介します。
災害・緊急事態が発生しても迅速に対応できる
BCPを策定すると、災害や緊急事態が発生しても迅速に対応できる体制を整えられ、損害を最小限にとどめられます。
計画に基づいて具体的な対応手順や役割分担が明確化されているため、混乱を最小限に抑え、迅速に行動に移すことが可能です。事業の早期復旧と損害の軽減はBCPを策定する主目的であり、最大のメリットです。
従業員の雇用や顧客への供給を守れる
BCPの策定は、顧客への製品・サービスの供給や従業員の生活を守ります。災害時や緊急時に事業の早期復旧ができれば、従業員の雇用を維持できるでしょう。雇用を守ることは従業員の家族を守ることにもつながるため、企業に対する従業員の満足度にも貢献します。
また、自社の業務が停止すれば、取引先や顧客への製品・サービス供給にも影響がおよびます。例えば、食品製造業において製品供給や物流が停止すると、業種を問わずサプライチェーン全体に影響を与えるおそれがあります。
緊急時の対応策を整えておけば、サプライチェーンの維持・早期回復が可能となり、取引先企業や顧客への影響を最小限に抑えることができるでしょう。
企業価値や信頼が向上する
BCPの策定により、災害時・緊急時の対策が万全な企業は対外的な評価も高まります。取引先からすると、災害時・緊急時の安全対策がなされていない企業は、事業継続能力に不安が残るでしょう。
BCP策定は、取引先選定基準にもなります。特に、規模の大きい企業にとって取引先の事業継続性は重要です。自然災害のリスクへの不安が高まっている日本では、今後、取引先の選定基準にBCP(事業継続計画)策定の有無を優先事項として挙げる企業が増加することも十分に考えられます。
競合他社との差別化や競争力を高めるため、戦略的にBCP策定を進める企業もあります。
企業の社会的責任を果たしていると評価される
BCPの策定は、CSR(企業の社会的責任)のひとつとして考えられています。BCPを策定し、災害や緊急事態発生時でも事業を継続できるようにすることは、以下の責任を果たすことにつながります。
| 分類 | 具体例 |
|---|---|
| 顧客への責任 | サービスや製品の供給を途絶えさせない |
| 従業員への責任 | 雇用の維持、安全確保 |
| 地域社会への責任 | インフラや経済活動の一部として機能を維持 |
| 取引先・サプライチェーンへの責任 | 連鎖的な事業停止を防ぐ |
BCPの策定や内容をCSRやコーポレート・ガバナンス、サステナビリティの取り組みのひとつとして企業ホームページに掲載している企業も少なくありません。
BCPを策定することにより、取引先だけでなく顧客、投資家や株主からの評価につながるため、経営戦略のひとつにもなります。
税制優遇等の公的支援を受けられる可能性が高まる
中小企業や小規模事業者がBCPを策定する前に取り組みやすい制度として、2019年7月から 「事業継続力強化計画」 の認定制度がはじまりました。事業継続力強化計画を作成し、経済産業大臣に認定を受けると公的支援を受けられます。
ただし、条件を満たしても必ず融資が受けられるわけではありません。税制優遇や公的支援の一例は以下のとおりです。
- ●日本政策金融公庫による低利融資
- ●中小企業信用保険法の特例
- ●中小企業投資育成株式会社法の特例
- ●日本政策金融公庫によるスタンドバイ・クレジット
- ●防災・減災設備に対する税制措置
災害時に有効なBCP策定方法から運用までの手順

BCPの策定方法や運用の手順を紹介します。
- ●【目的の設定】基本方針を決める
- ●【優先順位】重要業務・目標復旧時間を決める
- ●【現状認識】被害状況の想定と影響を考える
- ●【具体策】事前対策を行う
- ●【役割分担】緊急事態発生時の体制を考える
- ●【策定】BCP(事業継続計画)を策定する
- ●【浸透】全従業員や家族へ共有する
- ●【改善】定期的・継続的に見直す
なお、BCPを策定し、継続的な運用を図ることを 「BCM(Business Continuity Management、事業継続マネジメント)」 と呼びます。今回は、BCPを含めたBCM全体のプロセスを紹介するので、参考にしてください。
【目的の設定】基本方針を決め
まずはBCP策定の目的を明確にし、事業継続に向けた基本方針を設定します。会社全体の目指すべき方向性を決定する段階です。何のために策定するかを明確にしましょう。
目的や方針を決める際には、経営理念を振り返り、「自社は何のために存在する企業か」 等、基本的な原点に立ち返ってみてください。社会的責任や理念から、優先すべき事項や方向性等の基本方針が見えてくるかもしれません。
【優先順位】重要業務・目標復旧時間を決める
何を、どのような順で復旧するのかを決める段階です。中核事業を洗い出し、優先順位をつけます。中核事業とは、「会社の存続に関わる最も重要性(または緊急性)の高い事業」 です。
重要と思われる事業をいくつか挙げ、財務面、顧客関係面、社会的要求面から、優先順位を付けていきましょう。災害・緊急時に中核事業へリソースを集中すれば、迅速な復旧が可能になります。
【現状認識】被害状況の想定と影響を考える
地震や台風、感染症の流行等、考えられるリスクを想定し、現状のままだとどのような被害を受けるかを考える段階です。被害が事業に与える影響(売上の減少、顧客離れ、法的問題等)を具体的に評価することで、事前対策や復旧計画の優先度を決める基盤が整います。
受ける被害は業種によって異なります。例えば、感染症や地震の場合、医療機関では医療需要が増加します。一方、IT企業であれば、地震によって受ける被害はシステムエラーや停電による重要なデータの喪失等が考えられるでしょう。
自社の事業内容にあわせて具体的に想定し、影響度を評価することが大切です。
【具体策】事前対策を行う
リスクを最小化するために、具体的にどのような事前対策をとるかを決める段階です。想定される被害に対し、復旧に向けた行動計画を作成します。一例は以下のとおりです。
- ●安否確認ルールの整備と人員の確保
- ●非常用の電源設備の準備や代替手段の確保
- ●重要データの保存やバックアップ、情報収集・発信手段の確保
- ●復旧に必要な資金の把握と調達
- ●従業員のための物資(食糧や日用品)の確保
例えば、停電時に備え、非常用発電機や無停電電源装置(UPS)等を準備します。また、これらの設備が使用できない場合に備え、臨時の電力供給手段としてモバイルバッテリーや大容量のポータブル電源等の代替手段を検討し、災害時でも最低限の機器やシステムが稼働できるよう対策を講じます。
このように、中核事業の復旧を前提として優先順位を考えつつ、それぞれの内容を具体化していきましょう。
【役割分担】緊急事態発生時の体制を考える
災害発生時に迅速かつ適切に対応できるよう、誰が何をするのか、組織内での役割分担を決めます。統括責任者を任命しておく他、責任者が不在の場合の代理責任者も任命しておきます。
企業の規模や業務の役割分担に応じて人選するとより効果的です。それぞれの役割におけるリーダーとサブリーダーも決めておきましょう。
指揮をとる人や、各部門・従業員の具体的な役割、緊急連絡体制を明確にすることで、緊急時の混乱を避け、スムーズな対応が可能になります。
【策定】BCP(事業継続計画)を策定する
次の段階でBCPの策定を行います。リスク評価や対策内容、緊急時の具体的な行動手順等を文書化する段階です。最初から完璧な事業継続計画(BCP)を策定する必要はありません。
想定される状況ごとに実行可能な対応計画を記載し、現状 「できていること」 と 「できていないこと」 を把握することが大切です。
【浸透】全従業員や家族へ共有する
策定したBCPは経営層だけでなく、従業員へ周知・浸透させ、自分の役割を理解させる段階です。BCPを策定しても、従業員が内容を把握していなければ役に立ちません。
策定後は定期的な訓練やシミュレーションを行い、理解度を深めることも不可欠です。
【改善】定期的・継続的に見直す
BCPは策定して終わりではなく、定期的・継続的な見直しと改善が重要です。BCPの実効性を見直し、ブラッシュアップします。
更新頻度や更新を行う条件は企業の特性や規模によっても異なりますが、中小企業庁では、以下のタイミングで更新を行うことが推奨されています※。
- ●会社の組織体制に大きな変更があった場合
- ●取引先(供給元または納品先)に大きな変更があった場合
- ●会社の中核事業に変更があった場合
- ●新しい事業ライン、製品、またはサービスを開発した場合
- ●主要な情報通信システム、ネットワークに大幅な変更があった場合
- ●会社の業務に関連する、国や業界のガイドラインが改訂された場合
- ●サプライチェーンからの要求に変更があった場合
上記の条件に該当しない場合でも、1年ごとに見直し、最新の状態に保つことが推奨されています。
BCPが機能する災害の事例
従来の災害対応マニュアルは、リスクごとに対応方法を検討するものです。一方で、BCPは原因を問わず、被害を最小限に抑えるための迅速な対応に重点を置く計画を指します。
そのため、BCPはさまざまな災害・緊急事態に対して有効です。具体例は以下のとおりです。
| BCPが機能する災害 | 具体例な事例 |
|---|---|
| 自然災害 | 地震・津波、豪雨・洪水、台風等 |
| 事故・災害 | 火災、有害物漏洩、集団感染等 |
| 製品事故 | 人命にかかわる重大な事故や安全性の問題よる損害の発生、リコール等 |
| 人為的災害 | サイバー攻撃、社員による悪意ある機密情報の流出、法令遵守違反等 |
| 風評被害 | 誤った情報の拡散、製品に対する誤解、倒産の噂等 |
BCP策定・運用時の注意点やポイント
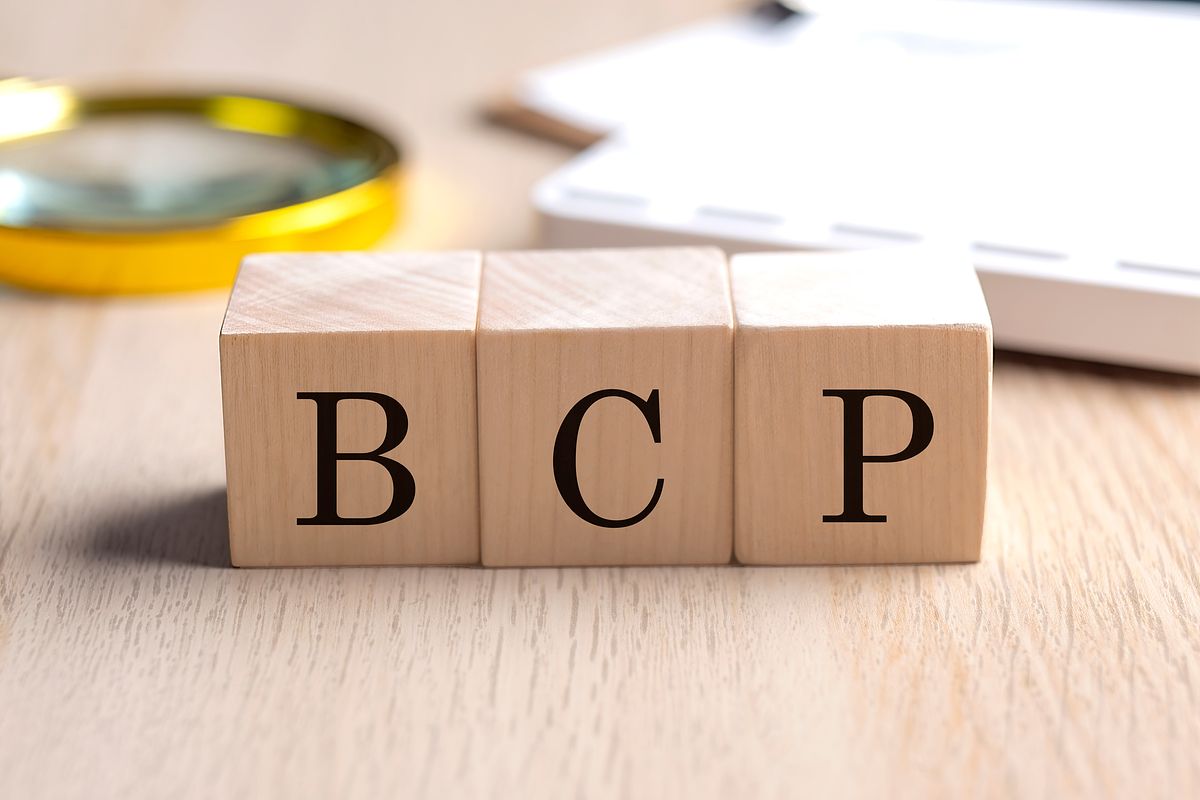
BCP策定・運用時には、以下の点に注意しましょう。
- ●自社にとって実現可能なBCPを策定する
- ●はじめから完璧を目指さない
- ●定期的な点検・見直しは必要不可欠
- ●災害時に有効なシステムを導入し併用する
自社にとって実現可能なBCPを策定する
現実的かつ実行可能なBCPを策定することで、非常時にも無理なく行動できます。自社のリソースや規模にあった計画を立て、過剰な負担がかからないようにしましょう。
また、BCP策定の大筋のガイドラインは同じですが、詳細は業種の特性にあわせる必要があります。各業界に関連する公的機関や団体からガイドラインが提供されているので、自社にあったものを参考にしつつ、実現可能なBCPを策定しましょう。
はじめから完璧を目指さない
BCPは、はじめから完璧なものを目指すのではなく、まずは基本的な対応を決めましょう。
事業の状況や外部環境は常に変化するため、最初からすべてのリスクを把握することは簡単ではありません。運用しつつ徐々に内容を見直せば、効果的なBCPへと改善できます。
定期的な点検・見直しは必要不可欠
BCPは一度策定すれば終わりではなく、定期的に点検・見直しを行うことが重要です。新しいリスクや技術の進展、社内の変化に応じて、内容を更新し、常に最新の状態に保ちましょう。
1ヶ月に1回や、1年に1回等、あらかじめ見直しを行うタイミングを決めておくと良いかもしれません。
災害時に有効なシステムを導入し併用する
BCPの効果を高めるためには、災害時に有効なシステム(安否確認システム、データバックアップシステム等)を導入し、併用することが重要です。BCPの業務をすべて人力で行うと人的リソースが不足してしまいます。必要に応じてBCPの策定・運用に役立つサービスやシステムを活用しましょう。
例えば、災害時や緊急時に従業員とスムーズに連絡がとれる安否確認システムを導入すると、事業の迅速な復旧に役立ちます。自社でシステムの構築や管理が難しいなら、月額で利用できる安否確認システムを導入すると業務を効率化できるためおすすめです。
災害時にBCPの迅速な実施をサポートする安否確認システム 「ANPiS」
BCPの策定をお考えなら、関西電力の 「ANPiS(アンピス)」 がおすすめです。
ANPiSは、気象庁と連携した安否確認システムで、災害時や緊急時はもちろん、平常時にも活用いただけます。災害時・緊急時に必要な機能を備えながら、シンプルで使いやすい操作設計となっています。
比較的低コストで導入でき、従業員への安否確認メールの自動配信や、回答結果の自動集計が可能です。手動でメール配信をすることもでき、部署やグループを絞った連絡にも活用できます。
災害時でも、システムの復旧を含む重要業務に、人的リソースをスムーズに集中させることができます。DR環境構築や災害対策にコストを割けない企業におすすめです。ANPiSで利用できる機能の一例は以下のとおりです。
【利用できる機能】
- ●気象庁の情報と自動で連携
- ●地域、震度、警報・注意報等種類に応じた配信設定
- ●従業員の回答結果を自動で集計
- ●未回答の従業員に対する自動再配信
- ●手動配信による柔軟な対応
- ●アンケートや会議の出欠確認等平常業務への応用
- ●安否登録の際のID・パスワードスキップ
- ●部門横断のグループ設定
- ●従業員家族の安否登録(最大4名まで)
- ●個人情報の秘匿性
- ●LINE配信 (有償オプション)
初期費用は無料、月額6,600円(税込)から利用可能で、企業の規模やニーズにあわせて2つのプランが用意されており、全国で利用可能です。
| ご利用人数 | スタンダードプラン※1(税込) | ファミリープラン※2(税込) |
|---|---|---|
| ~50名 | 6,600円 | 6,985円 |
| ~100名 | 9,900円 | 10,670円 |
| ~150名 | 13,200円 | 14,355円 |
| ~200名 | 15,400円 | 16,940円 |
| ~300名 | 17,600円 | 19,910円 |
| ~400名 | 19,800円 | 22,880円 |
| ~500名 | 22,000円 | 25,850円 |
| 501名~ | 100名ごとに+2,200円 | 100名ごとに+2,970円 |
Webからお申込みができ、2週間の無料トライアルも可能なので、安否確認システムの導入を検討する場合は、相談してみてはいかがでしょうか。
- スタンダードプランは、従業員とその家族へメール配信するプランです。
- ファミリープランは、スタンダードプランに加えて、家族の応答内容を家族内で共有することができます。
なお、家族への安否確認メールは管理者による手動配信となります。
BCP策定や災害対策システムの導入は競合との差別化になる
BCP(事業継続計画)とは、緊急時に事業を継続させるために策定するものです。日本は自然災害が多く、近年は大規模地震のリスクへの不安が高まっているため、BCPの重要性はより高まっています。
BCPの策定は、従業員の安全や顧客への安定したサービス提供だけでなく、事業継続性の向上により取引先へのアピールにもなる、企業の存続にとって重要な要素です。
しかし、BCPをすべて自社のシステムで対応しようとすると、リソースが不足するおそれがあります。必要に応じて、導入が容易な外部システムの活用も検討しましょう。安否確認システムの導入は、比較的ハードルが低いBCP対策のひとつです。
安否確認システムの導入なら、ぜひANPiSをご検討ください。ANPiSは関西電力が提供している安否確認システムで、災害時はもちろん、通常業務にも応用できる機能をもったシステムです。初期費用無料、月額6,600円から導入可能な他、無料トライアルも提供しています。
BCPの策定を検討するうえで、有効なシステムの導入を考えているのであれば、ぜひお気軽にご相談ください。
従業員の安否確認から
集計までを自動化
災害時の迅速な初動対応が可能に
安否確認システム 「ANPiS」 は気象庁と連携し、 災害が発生するとメール等が自動で配信され、
従業員の安否や出社可否の確認結果を自動集計します。

- ※1 2019年8月(サービス開始)~2024年9月現在の実績です。受信側の要因を除きます。
- ※2 オプションでLINEの一斉配信も可能です。

監修者 三沢 おりえ(みさわ おりえ)
総合危機管理アドバイザー
防犯・防災、護身術の講演会やセミナー、イベント、メディア対応等幅広く活動。日本一非常食を食べていると自負する非常食マイスターでもある。総合防犯設備士、危機管理士、防災士。
サービス概要資料
安否確認システム
「ANPiS」
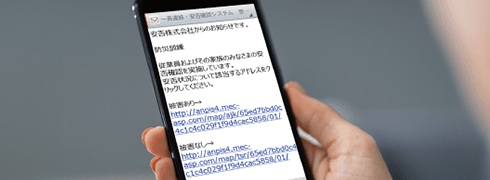
BCP策定の第一歩は、安否確認から!関西電力が提供する「安否確認システム(ANPiS)」のサービス概要をご紹介します。
資料の一部をご紹介
- 安否確認システム(ANPiS)とは
- 選ばれる理由
- サービスの特徴
- よくあるご質問
資料ダウンロードフォーム
■個人情報の取扱いについて
◇個人情報の利用目的
弊社では、「個人情報保護方針」内の「個人情報の利用目的」および「弊社が開催するセミナーの案内、弊社と提携する他社のセミナーの案内を行うために必要な範囲内で個人情報を利用いたします。
◇広告・宣伝メールの送信
弊社は、お申込フォームで入力いただいたメールアドレスあてに、広告・宣伝メール(「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」に定める「特定電子メール」を指します。)を送信することがあります。また、お客さまから申し出により、速やかに配信を停止します。